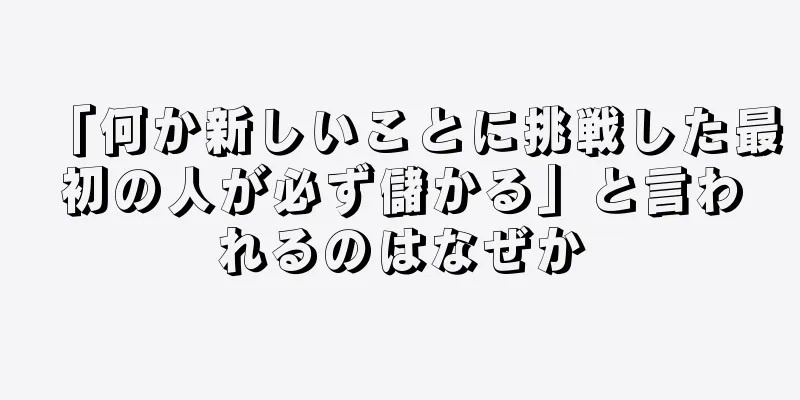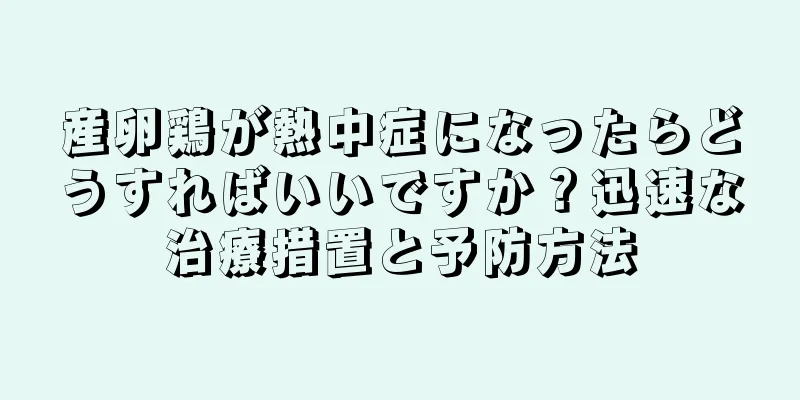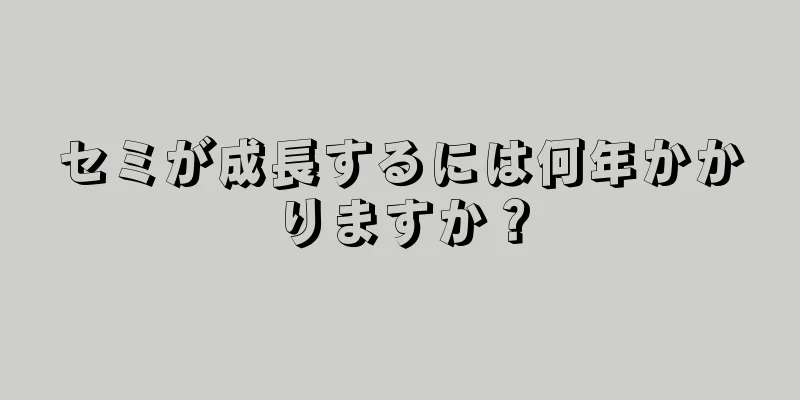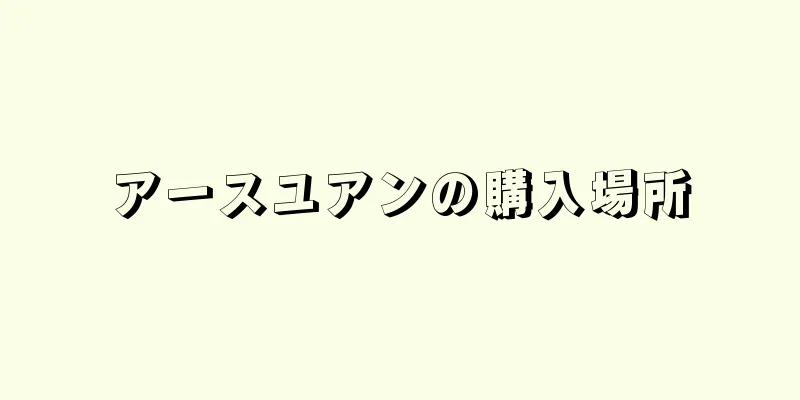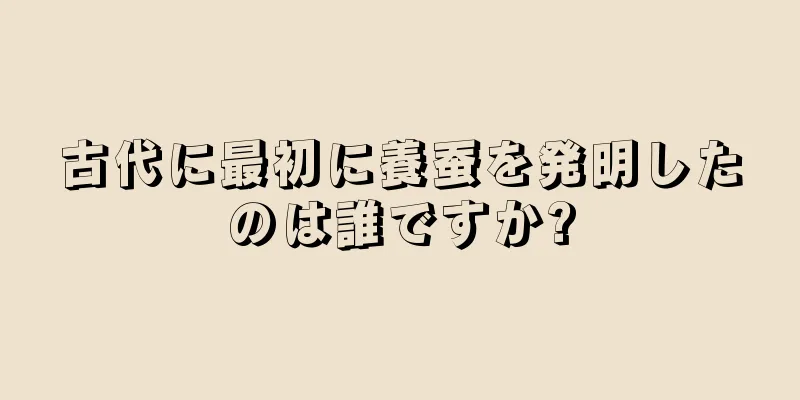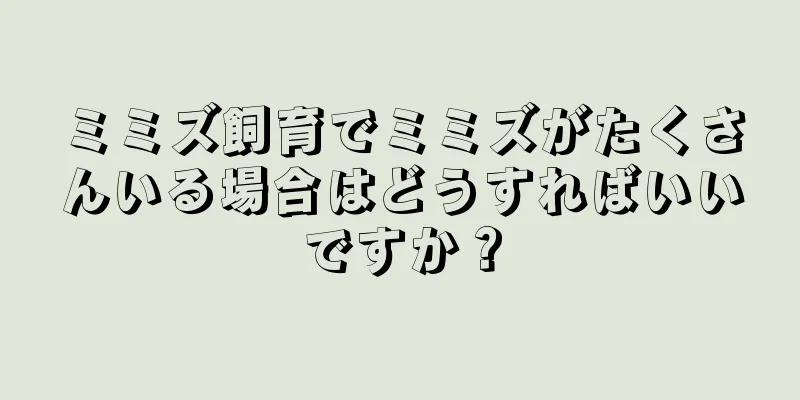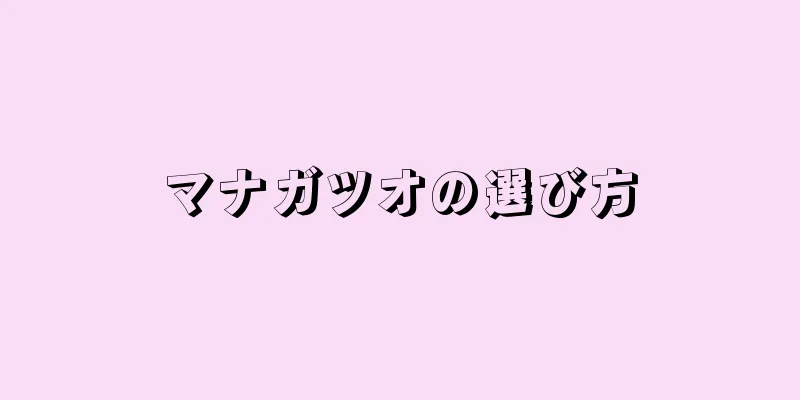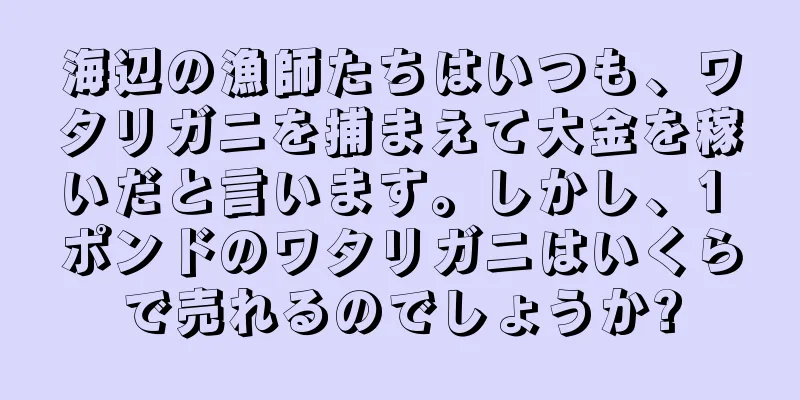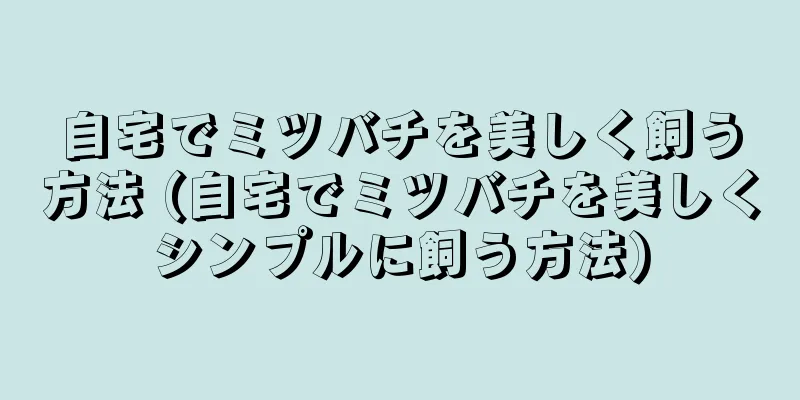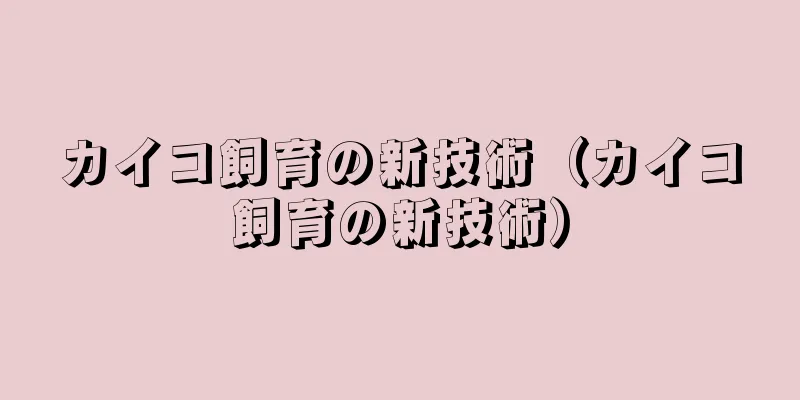日本の漁業の発展に影響を与える要因は何でしょうか?
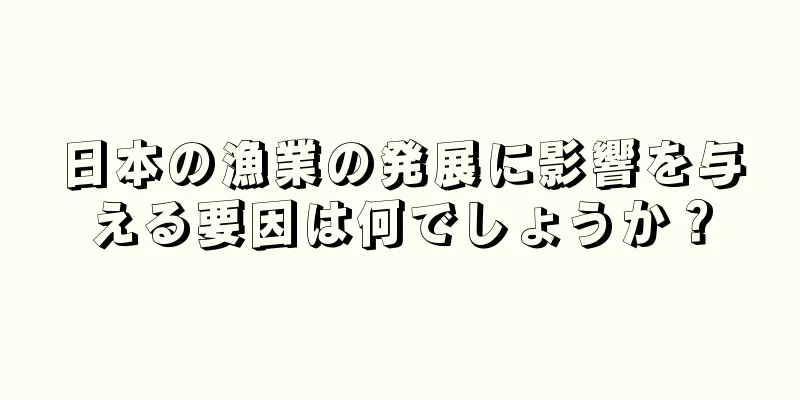
|
日本の漁業開発の現状 1. 日本の水産業の発展 日本は世界でも最も漁業が発達した国の一つであり、漁業を非常に重視しています。日本の漁場は黒潮などの影響を受け、魚類資源が豊富な世界三大漁場の一つとなっています。水産物は日本人の食生活において重要な位置を占めています。魚は日本人の食生活に欠かせない食品であり、日本人一人当たりの動物性タンパク質摂取量の40%以上を占めています。 1960年代以降、日本の漁業生産量は大幅に増加し、特に遠洋漁業が急速に成長しました。しかし、200海里排他的経済水域制度の施行や1973年に勃発した石油危機により、遠洋漁業は大きな打撃を受けました。 1970年代から1980年代にかけて、沖合漁業が成長し始め、徐々に日本の漁業の中心となってきました。近年、日本は養殖業を積極的に展開していますが、漁獲量は依然として緩やかな減少傾向にあります。日本の漁業生産量は1984年に1,282万トンのピークに達しました。その後、資源の減少や就業者の減少・高齢化により、1989年以降は減少傾向にあり、2002年には総漁業生産量は588万トン、総生産額は1,875.3億円にまで落ち込んでいます。 2004年の総生産量は578万トン、総生産額は1,603.6億円でした。 2005年は漁業総産出量が571万9000トンと1999年以降で最低となり、漁業生産額は1兆6007億円と前年より29億円減少した。 1960年から1990年までの30年間で、日本の水産物輸入量は約36倍に増加しました。 FAOの統計によれば、2003年の世界の水産物輸入量上位5カ国は、日本が321万トンで、次いで中国が232万トン、米国が224万トン、スペインが161万トン、デンマークが160万トンであった。輸出量上位5カ国は、ノルウェー214万トン、中国208万トン、ペルー172万トン、タイ140万トン、米国131万トン(日本は36万トンで24位)であった。 2003年の世界輸入額上位5カ国は、日本が126億2,400万米ドル、米国が117億5,800万米ドル、スペインが49億1,900万米ドル、フランスが38億300万米ドル、イタリアが35億7,100万米ドルであった。輸出額上位5カ国は、中国が53億6,200万ドル、タイが39億2,000万ドル、ノルウェーが36億6,900万ドル、米国が34億5,800万ドル、カナダが33億1,800万ドル(日本は9億5,200万ドルで22位)だった。 2. 日本の水産業の現状 1. 漁業と養殖 日本では、漁業生産を海面漁業(遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業を含み、我が国の漁業分類では、海面漁業と遠洋漁業にほぼ相当します)、海面養殖、淡水養殖、淡水漁業に分類しています。 海上漁業は常に日本の水産業の主要産業でした。生産量は継続的に減少しているものの、生産量の80%以上は依然として海洋漁業によるものです。生産規模別にみると、主な漁獲魚種はマグロ、カツオ、サケ、イワシ、アジ、サバ、サンマ、タラ、ヒラメ、イカなどである。2004年と比較すると、2005年の日本のサバの生産量は大幅に増加したが、イワシ、ホタテ、サケなどの生産量は減少した。ホタテ、サケなどの魚類の生産額は増加したが、カツオ、サンマ、マグロの生産額は減少した。海上漁業の総生産量は441万2千トンで、前年より4万7千トン減少した。総生産額は1,594億円で前年比0.6%の減少となった。 日本の海洋養殖生産量は近年120万トン以上を維持している。 2005年の海面養殖業の総生産量は121万1千トンで、ピークだった1994年の134万トンから12万9千トン減少した。2005年の海面養殖業の総生産額は4,392億円で、前年より49億円増加した。このうち、養殖業は、生産量26万9千トン(前年度比2.7%増)、生産額1,918億円(前年度比2.4%減)となった。貝類養殖は42万2千トン(前年度比6.4%減)、771億円(前年度比6.4%増)となった。海藻類は50万9千トン(前年比5.2%増)、金額は1,213億円(前年比2.4%増)となった。養殖の主な魚種は、魚類、マダイ、エゾホタテ、カキ、コンブ、昆布、ノリ、その他、ヒラメ、カワラヒラメ、アジ、エビ、マダラカキなどです。 2005年の日本の淡水漁業と養殖業の総生産量は9万6千トンで、ピークだった1979年の半分以下となった。このうち淡水漁業の生産量は5万4千トン、淡水養殖業の生産量は4万2千トンで、総生産額は1021億円で、前年より13億円減少した。淡水漁業の主な魚種は遡河性のサケ・マス、アユ、コイ、ハマグリ、ウナギなどです。淡水養殖の主な魚種はマス、アユ、コイ、ウナギのほか、フナ、スッポンなどです。1種の魚種の生産量は通常1,000トン未満です。 2. 水産物の加工と消費 日本の加工水産物は、主に塩蔵品、乾燥品、魚介類調味料、冷凍食品、油脂・肥料、冷凍生鮮品、缶詰などがあり、2005年の食用加工品総量は209万5千トンで、前年より3万9千トン減少した。主要品目の加工量は、塩製品209千トン、乾燥品334千トン、魚肉調味料655千トン、冷凍食品286千トン、冷凍生鮮品1625千トン、その他加工食品484千トンとなっている。 2005年は、乾物加工品の加工量が前年に比べ若干増加した以外は、冷凍食品、塩蔵食品、調味食品など加工量はいずれも程度の差はあるものの減少となった。 日本は水産物の主要消費国です。 2004年の国内水産物消費量は1,048万トンで、前年比5%減少した。そのうち食用水産物の消費量は80%を占め、これは1人当たり年間62.7kgに相当します。食べられない部分を除くと、一人当たり年間約34.5kgを消費することになります。 2004年、日本の食用水産物の自給率は55%で、2003年の57%から低下したが、これは主に国内漁業生産量の減少と輸入量の増加によるものである。統計によると、2005年の海藻の自給率は65%でした。 3. 水産物の流通と市場 日本には主な漁港が203ヶ所あります。 2005年の総漁獲量は約288万7000トンで、前年とほぼ同量であった。総漁獲額は5,255億円で、前年比約4%の減少となった。水揚げ量が10万トンを超える漁港は、焼津(22万9千トン)、銚子(21万5千トン)、石巻(15万8千トン)、八戸(14万9千トン)、釧路(11万9千トン)、気仙沼(11万6千トン)の6港だ。他に水揚げ量の多い港としては、松浦港、堺港、波崎港、枕崎港などがあります。 現在、日本国内の生産市場は約900カ所あり、流通量・金額ともに減少傾向にあります。小規模市場は取扱量が少なく市場機能が十分に発揮できない状況にあったため、2001年3月末に「水産物生産市場の統合・合理化に向けたガイドライン」を策定・公布し、これに基づき、すべての都道府県、道、郡において市場の統合が進められました。 2005年6月末までに、39の省、州、郡で33の水産物生産市場が縮小されました。 札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡など10の主要都市に中央卸売市場があります。平均価格の推移から判断すると、取引価格は総じて下落傾向にある。 2004年に取引された生鮮水産物、水産物加工品、冷凍製品の平均価格は、生鮮品が770円/kg、水産物加工品が730円/kg、冷凍製品が791円/kgとなり、前年とほぼ同額となった。サンマやカツオなどの漁獲量の減少により、主要産地の魚介類(貝類、海藻類を除く)の流通量は前年比3%減少し、平均価格は182円/kgと前年比5%下落した。市場取引量は減少しているものの、スーパーマーケットなど需要の高い主体が直接購入する量は増加している。 4. 水産物貿易 日本に輸入される魚介類のほとんどは生鮮品です。 2004年に日本が輸入した水産物の総量は348万5000トン、金額にして1637億1000万円で、前年に比べそれぞれ16万トン、679億円増加した。しかし、輸入量はピークだった2001年と比べ9%減少、金額では前回ピークだった1997年と比べ16%減少した。このうち、輸入額が1000億円以上のものは、エビ2380億円(総輸入額の約15%)、マグロ2337億円(約14%)、サケ・マス1036億円(約6%)などで、その他、輸入額の多いものは、カニ807億円、ウナギ製品657億円、たらこ598億円、エビ製品522億円、イカ437億円などとなっている。 2004年、日本は水産物42万トンを1,482億円相当輸出した。これは前年に比べ、それぞれ5,400トン、129億円増加した。輸出量は12年ぶりに40万トンを超えた。そのうち、貝類の輸出量や輸出額は減少傾向にあるが、マグロやタラなどの魚類は過去5年間で飛躍的に増加している。中国(香港とマカオを除く)の輸出量が最も多く、主な魚種はサケとタラです。香港は輸出額が最も大きく、真珠、乾燥貝類、乾燥ナマコが主な輸出品です。平均輸出価格は1キロ当たり350円で、前年の366円から4.3%下落した。 2004年、日本の水産物輸入量・金額上位5カ国・地域は、中国が66万5千トン、3,357億円(香港・マカオを除く、主にウナギ加工品、カニ加工品、冷凍エビ)、米国が39万2千トン、1,477億円(主にたらこ、冷凍タラ肉、サケ)、ロシアが19万9千トン、1,170億円(主に冷凍カニ、たらこ、冷凍サケ)、タイが24万8千トン、1,103億円(主にエビ加工品、冷凍イカ、生エビ・冷凍エビ)、台湾が18万6千トン、1,085億円(主に冷凍マグロ、活ウナギ、ウナギ加工品)となっている。 5. 資源の保護と拡散 日本は1996年に国連海洋法条約を批准し、その後TAC制度や輸出規制制度を導入した。 2001年、日本は漁業基本法を制定し、資源回復計画を立ち上げ、漁業努力総量規制(TAE)制度を導入しました。 日本は、法令や漁業組合、漁業者による自主規制により、漁獲可能量、漁獲努力量、漁船数、漁馬力等の制限、禁漁区・禁漁期間の制限、漁具・漁法の制限、漁獲可能サイズ制限等を設けているほか、水産資源の保護・増殖を重視し、水産資源の増殖・放流に向けた取り組みを継続的に強化するとともに、人工魚礁の建設に多額の資金を投入している。 日本には魚の放流と放流に関する比較的完全なシステムがあります。静岡県を例にとると、県温水利用研究センター(種苗生産・増殖、放流指導)、県水産振興基金(必要な資金の交付、放流活動の監督)、県水産試験場(放流活動の指導、放流効果の試験)からなる資源増殖推進協定協議会制度を設けている。伊豆、榛南、浜名湖の3つの地域協定協議会に分かれており、各市町の漁業組合が具体的な放流や統計、募金などの業務を担当しています。日本では、水産資源の状況、漁業強化・放流の実施、放流効果の評価、関連する研究などについて意見交換を行うため、毎年、国・地域の水産強化会議を開催しています。日本が毎年繁殖放流している魚類は、回遊速度が遅く、固着性の強いサンゴ礁生息性の魚種が中心です。近年では、サケ、マダイ、クロダイ、ヒラメ、マガレイなどの魚類、エビ、クロエビ、イトマキエイなどの甲殻類、アワビ、シャコガイ、エゾホタテなどの貝類、ウニなど種苗放流数が50億匹を超えています。 2004年に放流された主な魚種は、シロギス18.5億匹、マダイ1,980万匹、クロダイ328.1万匹、ヒラメ308万匹、イシビラメ2,461.3万匹、エビ1億3,464.5万匹、カニ2,701万匹、アワビ2,391.1万匹、赤貝63.8万個、ウニ7,464.3万匹などであり、放流数は前年より若干減少した。 日本は世界でも最も早く人工魚礁の建設に着手した国の一つであり、1955年以降、全国各地で様々な人工魚礁の建設が行われてきました。1975年には「沿岸漁業の振興に関する法律」が公布され、魚礁の整備、水産動植物の繁殖、沿岸漁業の保全という3つの公益事業の積極的な展開が求められました。国は毎年計画を策定し、補助金を交付し、農林水産省及び都道府県が条例に基づいて実施します。 30年以上の建設を経て、日本の漁場の10分の1以上に人工魚礁が設置され、年間平均投資額は30億元近くに上る。日本の人工魚礁は種類も構造も様々です。それぞれの海域の状況に応じて設置されます。同国は現在、深海に特大の岩礁を設置する技術を習得している。近年、日本は天然の海底藻場の保護と修復にも大きな重点を置いています。政府部門、漁業協会、漁業者はいずれも、保護、調査、分析、修復実験などの対応する作業に取り組んできました。 6. 漁業労働と個人漁業者の所得 2005年11月1日現在、日本の水産業従事者数は222,510人で、前年比8,490人減、3.7%減となった。漁獲量の減少と生産規模の縮小は、漁業従事者の減少の原因となっています。男女別にみると、男性は186,350人(構成比83.7%)、女性は36,160人(構成比16.3%)で、それぞれ前年度比3.7%、3.8%の減少となった。年齢層別では、60歳以上が46.9%と最も多く、40~59歳が38.6%、25~39歳が11.8%、15~24歳が2.7%となっている。若者の割合はどんどん少なくなっていますが、減少率はどんどん大きくなっています。 2005年の日本の海洋漁業における世帯当たりの平均所得は526万円(約34万2千人民元)で、前年より0.6%減少した。支出額は305万円で、前年度比1.2%の減少となった。個人所得は221万円で、2.0%の減少となった。支出の内訳は、燃料費が18.1%、減価償却費が16.2%、人件費が12.7%となっています。小型定置網漁業の収入は594万円、支出は346万円、個人所得は248万円となった。支出のうち、減価償却費は18.6%、人件費は12.5%、各種手数料は11.5%を占めた。農林水産省によると、原油価格の高騰により燃料費は前年比13.1%増加した。しかし、民間企業の支出が増加するのではなく減少した主な理由は、企業がコストを節約するために従業員の賃金を削減したためです。 3. 日本の漁業管理モデルと政策の方向性 漁業管理を担当する日本の政府部門には、農林水産省水産庁、農林水産技術会議、漁業管理委員会などがある。農林水産省水産庁の主な業務としては、漁業経営の改善、金融課税、水産物の加工・流通、漁業保険・共済、海洋生物資源の保護・管理、漁業指導・監督、水産に関する国際協定・協力、水産試験研究、漁業の増進・放流、漁場保全、漁港、漁場・沿岸の一体化、漁業災害復旧などがある。 農林水産技術会議は水生試験研究に関する政策を担当しています。 水産管理委員会は、主に周辺海域の水産資源の管理を行い、単一の市、道、県、郡に収まらない回遊魚などの水産資源の管理を行っています。資源回復計画の見直し、適切な資源管理対策の決定など。 日本漁業協同組合連合会(略称「漁協」)は、日本国内の多数の中小漁業者と漁業者によって構成される経済連携組織です。また、政府と漁業者の間の仲介役を果たし、草の根の水生管理業務を担う機関でもあります。日本漁業協同組合の主な機能は、漁業行政、漁業管理、漁業研究開発などです。このうち、漁業行政には、共同漁業権、地域漁業権、定置漁業権の割り当て、公害防止、資源増強活動などが主に含まれています。漁業に関する業務には、融資の取得及び実行、燃料、網、養殖設備などのバルク品の購入、販売及び指導、製氷及び冷凍冷蔵事業、施設利用サービスなどが含まれます。水産研究開発とは、主に教育、研究、後援、各種学習会への参加など、教育および指導者育成活動を指します。 日本政府は、国際及び国内の漁業情勢並びに漁業の実際の発展に鑑み、公海を含む漁業資源の回復及び管理の強化に重点を置いた関連政策及び措置を調整する意向である。国際競争力のある漁業経営体の創設省エネ型漁業生産の発展を促進する。水産物の流通・加工の合理化を推進し、消費者に信頼される情報開示体制を確立する。漁村の活性化と健全な生態系の確保に向けた政策の策定と実施。 現在の日本の水産政策の焦点は、資源管理と環境保護を前提とした水産改革の推進である。漁業管理と技術の人材を育成し、国際的に競争力のある漁業管理団体を構築すること。流通と販売の合理的な発展を促進すること。世界貿易機関(WTO)と自由貿易協定(FTA)の交渉プラットフォームを最大限に活用し、水産物貿易の発展を促進する。 日本の産業全体の機械化が進んでいます。漁業も機械化が進んでいます。造船技術は進歩しており、エンジニアリングは高性能です。各漁船には魚群探知機が装備されており、沿岸、沖合、深海で操業します。 漁師の乗組員たちも、漁師たちの漁船の状況を知りたがっていました。漁獲量はかなり多いです。 世界各国が海洋資源に注目するようになり、日本の漁場は大きく縮小した。海岸の埋め立てや土地の干拓により、魚が成長し繁殖する生息地が破壊されます。産業廃水や下水の排出により沿岸の水質が汚染され、日本の漁業の発展に影響を及ぼしています。 日本の漁業条件は非常に良いが、市場は限られている。 海洋資源が豊富な沿岸国。 |
<<: これは何の魚ですか?それはティラピアだと言っていました。 。 。
推薦する
販売できるほどのライギョを育てるには何ヶ月かかりますか?
子どもの頃、夏休みに昆山へ行き、一日中従兄弟の後をついて歩きました。私のいとこは恐れを知らない男です...
ミツバチを飼育するときに蜂の巣を購入する必要がありますか?自分で作ることはできないのでしょうか?
1. ミツバチを飼育するときに蜂の巣を購入する必要がありますか?自分で作ることはできないのでしょう...
猫の目にあなたがどう映っているか教えて
あなたは猫にとって何ですか?猫は家にいる人それぞれに異なる反応を示します。実際、これらの反応は猫が目...
カタツムリ、イナゴ、ナミバッタはすべて害虫ですか?
1. カタツムリ、イナゴ、ナマコはすべて害虫ですか?個体数が多いと、作物に壊滅的な被害を与える可能...
カイコの育て方(カイコの育て方とは)
1. カイコに餌を与える正しい方法は何ですか? 1.給餌方法: 4~5歳の蚕は成虫となり、生育に適...
バッタを飼育するとお金が儲かるのでしょうか?知乎の記事の内容は何ですか? (バッタの飼育は儲かるのか?知乎の記事の内容とは?)
1. イナゴを飼育すると利益が出るか?育種コストには主に苗代、温室建設費、人件費、その他の費用が含...
ミミズにはどのくらいの頻度で餌を与えるべきですか?
1. バケツに入ったミミズにどのくらいの頻度で餌を与えるべきですか?回答:半月に1回餌を与えてくだ...
豚の繁殖率の計算方法と重要性
豚の繁殖率は繁殖効率を測る重要な指標の一つです。一定期間内の豚の総頭数に対する飼育豚の頭数の割合を指...
蚕の飼育方法と技術(蚕の飼育技術)
1. カイコの飼育方法は? 1. カイコ飼育の手順(1)カイコアリからカイコの赤ちゃんへ適温:20...
私は東莞にいます。ミシシッピアカミミガメはいつ冬眠を始めるのでしょうか?
私は東莞にいます。ミシシッピアカミミガメはいつ冬眠を始めるのでしょうか?時期は場所によって異なります...
豚の出産日を計算する方法を学ぶ
豚は重要な家畜の一つであり、農業生産において重要な役割を果たしています。豚の分娩日を計算する方法を理...
コイとオオゴイの主な違いは何ですか?
1. 異なる家族ハクレン(銀鯉)は、オオコナガ鯉、コイ、クロコイとも呼ばれ、コイに似ています。体は...
カイコ飼育観察15日間の記録シートの書き方(カイコ飼育観察15日間の記録シートの書き方)
1. カイコ成長記録シートの記入方法は?カイコの成長記録には、まず時間の記録、次に温度の記録が含ま...
今では畑にミミズがほとんどいないことに気づきました。これはなぜでしょうか?
今では畑にミミズがほとんどいないことに気づきました。これはなぜでしょうか?ミミズは環形動物であり、主...
ムカデの育て方 ムカデの育て方
ムカデの育て方 ムカデの育て方こんにちは!ムカデの繁殖方法: 1. 飼育箱は木の板で作られており、そ...