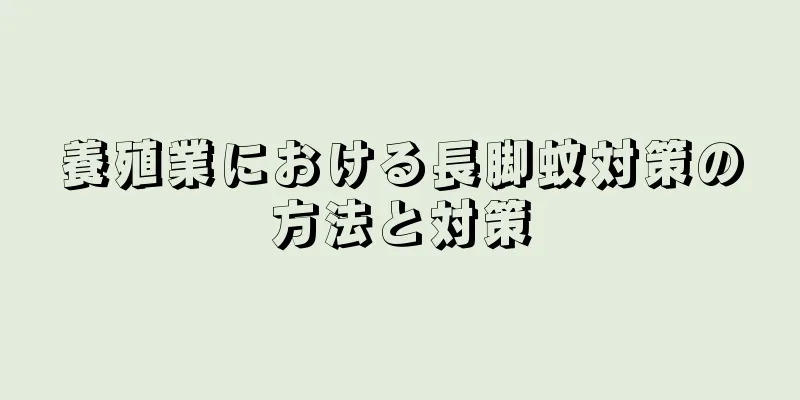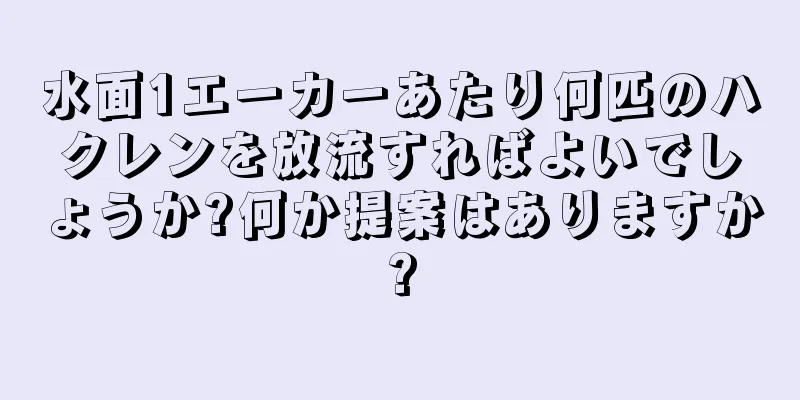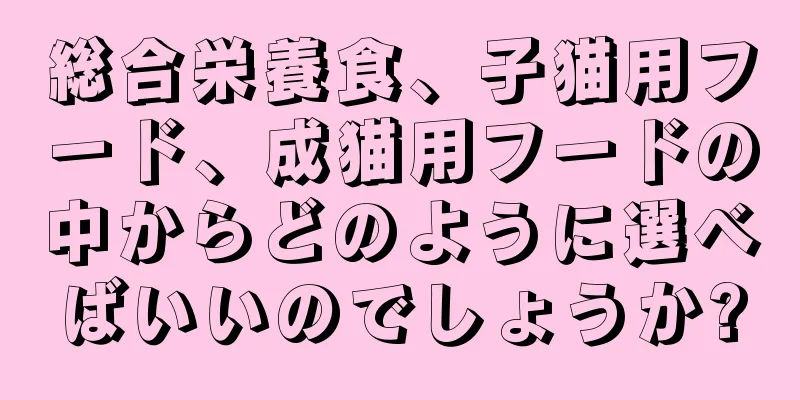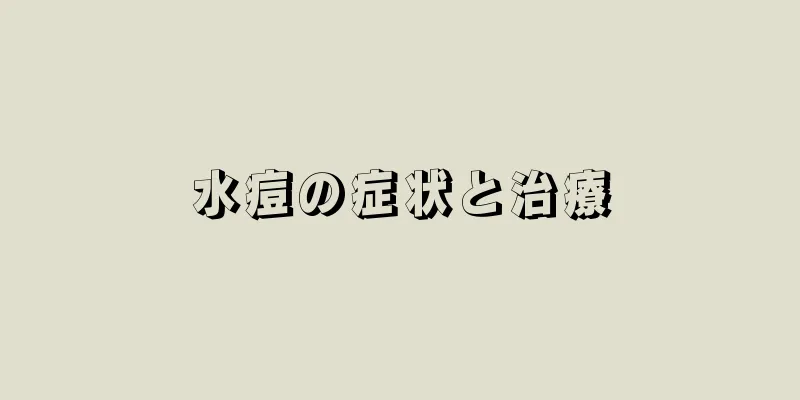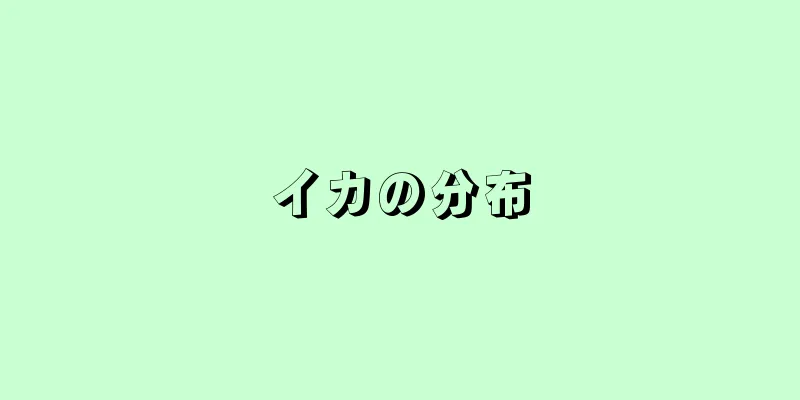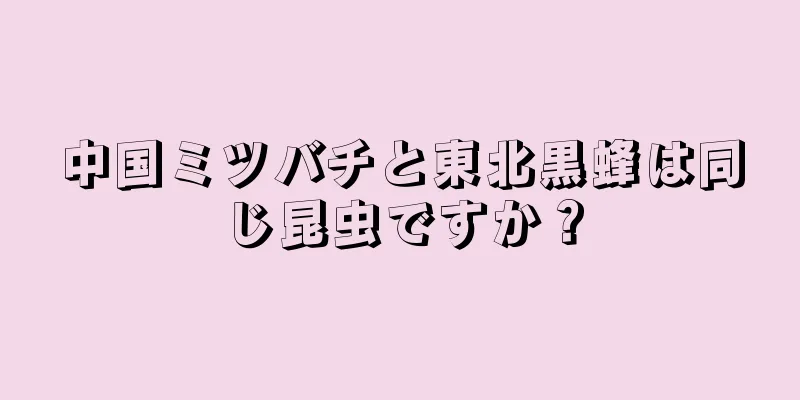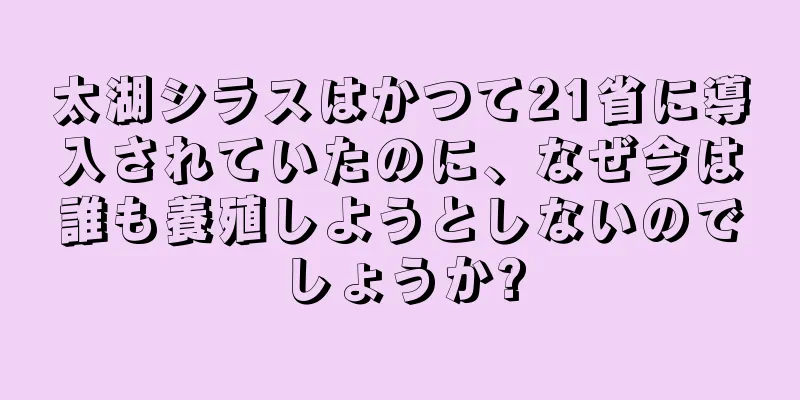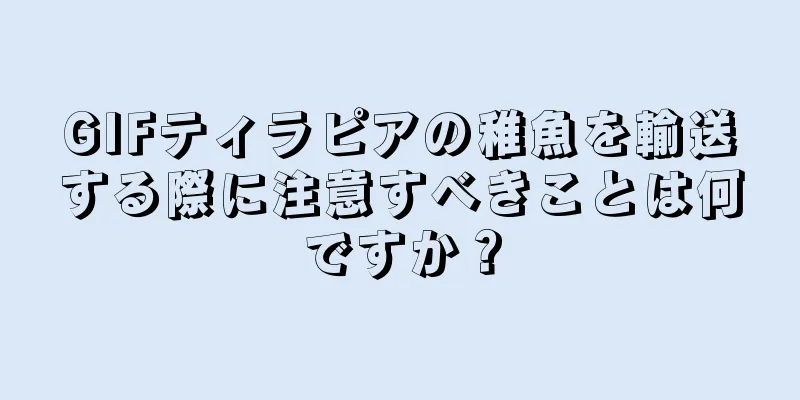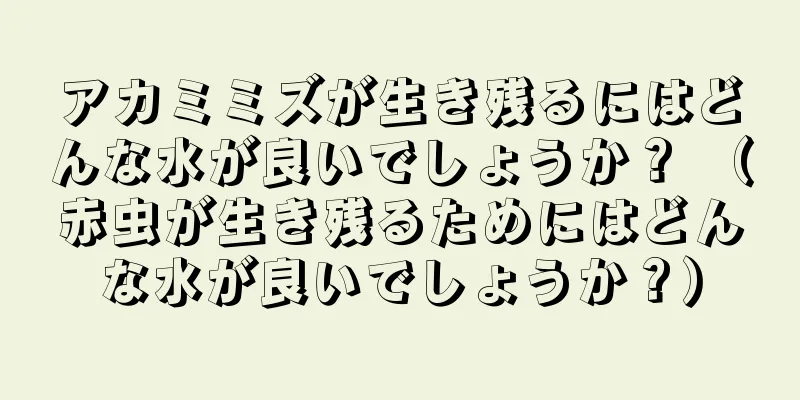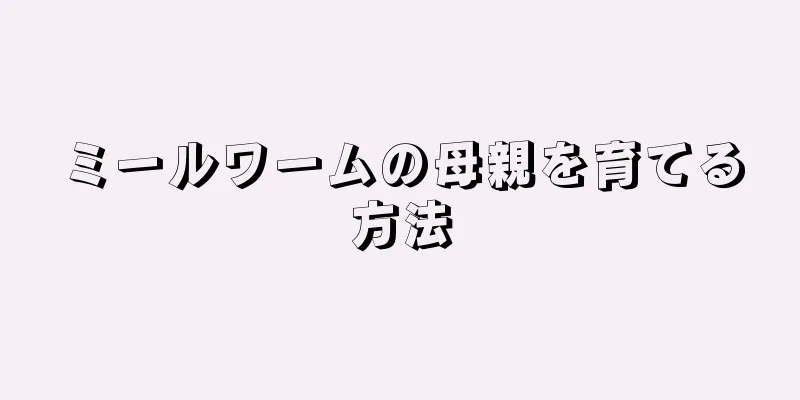セミの成長周期や習性はどのくらいですか?
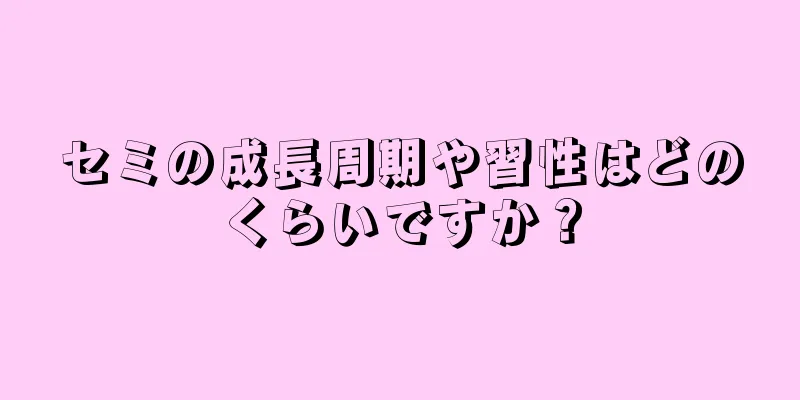
|
セミのライフサイクルは固定されていません。セミの種類によってライフサイクルは異なり、長いものも短いものもありますが、最長でも 17 年を超えることはありません。生物学者によると、中国のセミのライフサイクルは主に3〜7年、フランスのセミのライフサイクルは主に4年、北米のセミのライフサイクルは13〜17年で、これはセミのライフサイクルの中で最も長いことが知られています。セミにはいろいろな習性があります。彼らの習慣とライフサイクルについて話しましょう。 リスト: 1:セミの習性:セミ科昆虫の代表種。オスは腹部に発音器官を持っており、鋭い音を連続的に出すことができます。メスは音を出さないが、腹部に聴覚器官を持っている。幼虫は土の中で植物の根を吸いながら生活し、成虫は植物の樹液を食べて生活します。セミは不完全変態で、卵から幼虫になり、数回の脱皮を経て、蛹期を経ずに成虫になります。トンチャンは仏教から来ています。セミの幼虫は土の中に生息し、比較的強い一対の掘削用前脚を持っています。刺して吸う口器を使って植物の根から樹液を吸い取り、木を弱らせ、枝を枯らし、木の成長に影響を与えます。通常、それらは 3 年、5 年、17 年など、数年間、あるいは 10 年以上土の中に留まります。これらの数字には共通点が 1 つあります。それは、すべて素数であるということです。これは、素数には因数が非常に少ないため、他のセミと一緒に土から出てきて、領土や食物をめぐって競争することを防ぐことができるためです。 2: セミのライフサイクル: 実際には、7日間しか生きられないセミは存在しません。セミの寿命は最長で約70日にも達します。セミは世界で最も長生きする昆虫だと考えられています。セミのライフサイクルは場所によって異なります。例えば、フランスのセミのライフサイクルは一般的に 4 年ですが、北米では 17 年まで生きるセミもいます。一般的に、中国のセミの寿命は3~7年で、そのうち約半数は5年のライフサイクルを持っています。セミが夏にしか見られないのは、セミは土から出てセミに変身するまで、その一生のほとんどを土の中で過ごすからです。 セミは幼虫として一生のほとんどを地中の巣穴で過ごし、通常は数年、あるいは3年、5年、17年など10年以上土の中にとどまります。これらの数字には共通点が 1 つあります。それは、すべて素数であるということです。幼虫が土から出て成虫になった後の寿命は最長で約60~70日です。 セミは通常、夕暮れ時や夜間に出現します。この時期、幼虫は地面から這い出て木に登り、「脱殻」の過程を始めます。脱皮後しばらくすると、セミの羽は硬くなり、飛び始めます。 6月下旬になると幼虫が成虫に成長し始め、新しく現れたセミは緑色になります。このとき、オスはセミの鳴き声を使ってメスを誘い、交尾をさせる必要があります。 7月下旬から成虫の雌が産卵を始め、8月上旬から中旬にかけて産卵のピークを迎えます。ほとんどの卵は4〜5 mmの太さの枝に産み付けられます。メスのセミが産んだ卵は、2年目まで幼虫に孵化せず、地中に潜って新たなライフサイクルを開始します。 追加情報 夏の蝉の鳴き声 鳴くセミは完全な発音器官を持つ雄のセミです。メスのセミは発音器官が未発達なので鳴きません。オスのセミの腹部にある発音器官は太鼓に非常に似ており、振動すると音が出ます。発声筋は1秒間に約10,000回収縮することができます。耳蓋と鼓膜の間には空間があり、共鳴の役割も果たすため、蝉の鳴き声は特に大きくなります。 雌のセミは鳴き声から、声の主が健康で繁殖能力があるかどうかを大体理解できる。メスのセミは、少し考えた後、気に入ったオスのセミのところへ飛んで交尾を完了します。 参照元:人民日報 - セミの寿命はたった1ヶ月?間違っている! 17歳の蝉がいる場所がある 参照元: Baidu 百科事典 - 蝉 セミのライフサイクルはどれくらいですか?また、その習性は何ですか? ライフサイクル: すべてのセミが17年間も地中に留まるわけではない。それらのほとんどは2〜3年間土の中に留まります。一般的に言われる17年蝉は蝉の一種に過ぎません。北米には、17 年という非常に長いライフサイクルを持つセミの一種がいます。その生活習慣は非常に特殊です。生涯の最初の17年間は、地中に埋もれた幼虫の形で生きます。 17 年が経過すると、土から掘り出し、成虫となって現れ、交尾し、卵を産み、そして死んでいきます。 同じライフサイクルを持ちますが、13 年周期の別の種類のセミが存在します。自然界には 13 年と 17 年のセミは存在しますが、14 年、15 年、16 年のセミは発見されていません。セミはなぜそのライフサイクルとして 14 年、15 年、16 年ではなく 13 年と 17 年を選んだのでしょうか?その答えは数学における「素数」に関係しています。 セミの天敵のライフサイクルが2年、つまり2年に1度天敵が大量発生するとすると、14年と16年のセミが土から出てくるときには、必然的に天敵に遭遇することになります。天敵のライフサイクルが3年または5年であれば、15年ゼミは天敵に遭遇することになります。つまり、セミが天敵に遭遇した場合、その天敵のライフサイクルがセミのライフサイクルの要因となるのです。 そうすると、セミが食べられる可能性が大幅に高まります。 15年ゼミが一度土中から大量に出てきたときに、3年周期の天敵に大量に狩られてしまうと、次に土中から出てきたときにも必ず同じ運命をたどることになる。 17年周期の蝉だったらどうなるでしょうか?今年、土から出てきたときに3年周期の天敵に遭遇するとすれば、次にこの天敵に遭遇するのは42年後となる。その間に、安全に土から出て次の世代を繁殖させる機会があと 2 回あります。そのため、素数を周期とするセミの生存率は大幅に向上し、自然界でも生き残ることができるようになります。 生活習慣: 1. セミの幼虫は土の中に生息し、一対の強力な掘削用前脚を持っています。刺して吸う口器を使って植物の根から樹液を吸い取り、木を弱らせ、枝を枯らし、木の成長に影響を与えます。 2. 蝉の蛹の背中に黒いひび割れが現れると、脱皮が始まります。最初に頭が出て、次に緑色の体としわのある羽が出てきます。羽が硬くなり色が濃くなるまでしばらく留まり、その後飛び立ち始めます。 3. 6月末になると、幼虫が成虫へと成長し始めます。新しく羽化したセミは緑色をしており、寿命は最長で約60~70日です。 4. 木の上で大きな鳴き声を出し、針のような口器で樹液を吸います。幼虫は土の中に生息し、根から樹液を吸い取るため、木に害を及ぼします。 5. 脱毛はホルモンによって制御されます。蝉の蛹の前足は鉤状になっており、成虫が殻から出てきたときに木にしっかりとぶら下がることができる。 6. セミは喉が渇いたりお腹が空いたりすると、硬い口器を木の幹に差し込んで一日中樹液を吸い、大量の栄養分と水分を体内に吸収して寿命を延ばします。 7. オスのセミは鳴くことができます。彼らの発音器官は、鼓膜で覆われた大きな太鼓のように、腹筋にあります。鼓膜が振動して音が出ます。鳴筋は1秒間に約1万回伸縮するため、耳介と鼓膜の間に空間があり共鳴しやすく、鳴き声は特に大きくなります。 セミの成長期間と習性はどのくらいですか? 蚕のライフサイクルは、卵→幼虫→蛹→蛾の4つの段階を経ます。 蚕の成長と発育は温度、湿度、餌などに関係します。孵化期間は通常10~11日です。幼虫期は約25日間(具体的には、1齢4~5日、2齢3~4日、3齢4日、4齢6日、5齢6~8日)、蛹期は14~18日間です。蚕蛾の期間は3~5日です。 蛹から抜け出した後、カイコガは何も食べなくなり、羽が硬くなるのは約 1 時間後になります。羽が硬くなったら交尾します。雌の蛾1匹あたり約300~500個の卵を産みます。 蚕が蛾に変身する目的は交尾して卵を産むことです。 カイコの卵:カイコは卵によって繁殖します。カイコの卵は、幅約1 mm、厚さ約0.5 mmの小さなゴマによく似ています。雌の蛾は400~500個の卵を産むことができます。 1700~2000個の蚕の卵の重さは約1グラム、直径は0.2センチです。産まれたばかりの蚕の卵の色は、淡黄色または黄色です。 1~2日後には薄小豆色や小豆色に変わります。 3~4日後には灰緑色または紫色に変わり、それ以上変化しなくなります。これを固定色といいます。蚕の卵は外側が硬い卵殻で、内側に卵黄と漿膜があります。受精卵の中の胚は発育の過程で継続的に栄養を吸収し、徐々にカイコへと成長します。卵殻から這い出て、中身が空になった後は卵殻が白または淡黄色になります。 第一齢は4~5日です。 2齢幼虫は3~4日です。 3齢幼虫は4日です。第4齢は6日です。第 5 齢は 7 日から 9 日です。蛹の期間は14日から18日です。蛾の段階は3〜5日です。 蟻蚕:卵から孵ったときの蚕の体は茶色または黒色で、非常に小さく、細かい毛で覆われています。見た目がアリに似ているのでアリカイコと呼ばれています。アリカイコは長さ約2mm、幅約0.5mmです。卵殻から這い出てから2~3時間後に桑の葉を食べます。 蚕の睡眠習慣:蚕は桑の実をたくさん食べるので、成長がとても早く、体の色もだんだんと明るくなります。しかし、食欲は徐々に減退し、完全に食べなくなってしまうこともあります。少量の糸を吐き出し、腹足を蚕座に固定し、頭と胸を上げて、眠っているかのように動きを止めます。これを「睡眠」といいます。眠っている蚕は外見上は動かないように見えるかもしれませんが、その体は脱皮の準備をしています。古い脱皮を終えた蚕は新たな成長段階に入り、幼虫の段階から繭を作る段階まで4回脱皮をします。休眠状態はカイコの成長特性の一つです。これは蚕の遺伝的特徴であり、環境の影響も受けます。現在、私の国で飼育されている蚕は四睡種です。 カイコの年齢: 年齢とも呼ばれ、カイコが特定の発育段階にあることを示します。アリのカイコが初めて脱皮した時から第一齢となります。冬眠から目覚めた後、2齢幼虫期に入ります。再び脱皮した後、第3齢幼虫になります。 3回目の脱皮後、第4齢幼虫となり、第4回目の脱皮は長期冬眠とも呼ばれます。長い冬眠の後、5齢幼虫期に入ります。 5齢蚕は成長が非常に早く、体長は最大6~7cm、体重はアリ蚕の約1万倍にもなります。 成熟した蚕:蚕が第 5 齢の終わりに達すると、徐々に成熟の特徴を示します。まず、排泄する糞が硬いものから柔らかいものに変わり、濃い緑色から葉の緑色に変わります。食欲が減退し、食べる量も減少します。前消化管が空になり、胸部が透明になります。その後、完全に食べるのをやめ、体が短くなり、腹部が透明になる傾向があります。頭と胸を上げ、口から絹糸を吐き出し、繭を作る場所を探すために左右に上下に揺れ動きます。このような蚕を成蚕といいます。 カイコ 成虫期の繭作り:成虫になった蚕を専用の容器や繭の上に置くと、蚕は糸を吐いて繭を作ります。 繭作りは4つのステップに分けられます。1. 成熟したカイコはまず糸を紡ぎ出し、それが繭作り装置に付着し、次に糸を紡いで周囲の繭枝をつなぎ、繭作りの支え、つまり繭作りネットを形成します。繭ネットは繭の形をしているわけではなく、繭を支える役割を果たす、柔らかく乱雑な繭の絹の層です。 2. カイコは繭を作った後、繭の内側の層を厚くするために、乱雑な糸の輪を作り続けます。そして、S字型に糸を紡ぐと、繭の輪郭が現れ始めます。これを繭衣と呼びます。繭の絹繊維は細くて脆く、非常に不規則に配列されており、多量のセリシンを含んでいます。 3. 繭が形成された後、繭腔は徐々に狭くなり、蚕体の前端と後端は後ろに向かって曲がり、「C」字型を形成します。蚕は繭糸を吐き出し続けて、紡ぎ方がS字型から∞型に変化し、繭作りが始まります。 4. 大量の糸を紡ぐことにより蚕の体が大きく縮小すると、頭や胸部の揺れの速度が遅くなり、一定のリズムがなくなります。糸紡ぎが乱雑になり始め、蛹の裏地と呼ばれるゆるくて柔らかい繭の糸層が形成されます。 蚕の蛹:蚕は繭巣で繭を作り、約4日後に蛹になります。蚕の蛹の体は紡錘形をしており、頭部、胸部、腹部の3つの部分から構成されています。頭は非常に小さく、複眼と触角を持っています。胸部には胸脚と翼がある。膨らんだ腹部には 9 つの節があります。専門家は、蚕の蛹の腹部にある線や茶色の斑点から性別を判別することができます。蚕が蛹になったばかりの頃は、体の色は淡黄色で、蛹は柔らかくて柔らかいです。だんだんと黄色や黄褐色、茶色に変わり、蛹の皮膚も硬くなっていきます。約12~15日後、蛹は再び柔らかくなり始め、蛹の皮膚は少ししわが寄って土のような茶色になり、蛾に変わります。 カイコの蛹 カイコガ(成虫):カイコガは蝶のような形をしており、白い鱗粉で覆われていますが、2対の羽が小さいため、飛ぶ能力を失っています。カイコガは球形の頭部を持ち、膨らんだ複眼と触角を持っています。胸部には3対の胸脚と2対の翼がある。腹部には腹脚がなく、末端節は外性器に進化している。雌の蛾は大きく、ゆっくりと這います。雄の蛾は小さく、より速く這い、交尾相手を探すときには羽を素早く振動させます。通常、メスの蛾は交尾後 3 ~ 4 時間で受精卵を産みます。オスは交尾後に死に、メスは一晩で約500個の卵を産み、その後ゆっくりと死んでいきます。 蚕が産んだ卵→孵化→蛹→蛾へと変化し、新たな世代が生まれるサイクル。これがカイコの生涯です。 習慣 カイコは変態した昆虫です。最も一般的なのは、家蚕としても知られる桑蚕で、桑の葉を食べて絹の繭を作る経済的な昆虫の 1 つです。蚕は中国原産です。発育温度は7~40℃、繁殖適温は20~30℃です。蚕は桑の葉を食べます。桑の葉を継続的に食べると、体が白くなります。しばらくすると、皮膚が脱皮し始めます。換毛期は約 1 日続き、その間は寝ているときのように、食べたり動いたりしません。これを「冬眠」といいます。一度脱皮すると2齢幼虫になります。脱皮するたびに1歳ずつ年をとります。幼虫は合計4回脱皮し、5齢幼虫になります。その後、さらに8日間桑の葉を食べ、成熟したカイコとなり、糸を紡いで繭を作り始めます。 すべてのセミが 17 年間も地中に留まるわけではありません。ほとんどは2~3年間土の中に留まります。あなたがおっしゃった17年蝉は、蝉の一種にすぎません。北米には、17 年という非常に長いライフサイクルを持つセミの一種がいます。その生活習慣は非常に特殊です。生涯の最初の17年間は、地中に埋もれた幼虫の形で生きます。 17 年が経過すると、土から掘り出し、成虫となって現れ、交尾し、卵を産み、そして死んでいきます。同じライフサイクルを持ちますが、13 年周期の別の種類のセミが存在します。自然界には 13 年と 17 年のセミは存在しますが、14 年、15 年、16 年のセミは発見されていません。セミはなぜそのライフサイクルとして 14 年、15 年、16 年ではなく 13 年と 17 年を選んだのでしょうか?その答えは数学における「素数」に関係しています。セミの天敵のライフサイクルが2年、つまり2年に1度天敵が大量発生するとすると、14年と16年のセミが土から出てくるときには、必然的に天敵に遭遇することになります。天敵のライフサイクルが3年または5年であれば、15年ゼミは天敵に遭遇することになります。つまり、セミが天敵に遭遇した場合、その天敵のライフサイクルがセミのライフサイクルの要因となるのです。そうすると、セミが食べられる可能性が大幅に高まります。 15年ゼミが一度土中から大量に出てきたときに、3年周期の天敵に大量に狩られてしまうと、次に土中から出てきたときにも必ず同じ運命をたどることになる。 17年周期の蝉だったらどうなるでしょうか?今年、土から出てきたときに3年周期の天敵に遭遇するとすれば、次にこの天敵に遭遇するのは42年後となる。その間に、彼らには土から安全に出て次の世代を繁殖させる機会があと 2 回あります。そのため、素数を周期とするセミの生存率は大幅に向上し、自然界でも生き残ることができるようになります。 |
推薦する
黄色いナマズのオスとメスの見分け方
二次性徴:メスのキバナマズの腹鰭の後ろには、肛門、生殖口、排尿口があります。背中から持ち上げると卵巣...
ホタルはどのような気候や環境で一番長く生きられるのでしょうか? (ホタルはどの季節によく現れますか?)
1. ホタルは死ぬまでにどれくらい生きますか?ライフサイクルはどのくらいですか?住環境はどうですか...
バッタを飼育する際に注意すべきことは何ですか?
バッタを飼育する際に注意すべきことは何ですか? 1. 卵を孵化させる際の注意事項:イナゴの卵を孵化さ...
ニジマスの稚魚が急速に死につつあります。目が飛び出し、背中が黒くなっています。原因は何でしょうか。どうすれば治りますか。
1. ニジマスの稚魚が急速に死につつあり、目が飛び出し、背中が黒くなっています。原因は何ですか、ま...
カイコを育てるときに注意すべきことは何ですか?
1. カイコを育てるときに注意すべきことは何ですか?夏秋蚕飼育では注意すべき点1.農薬中毒を防ぐ。...
カタツムリの餌として最適な土はどのようなものでしょうか?
1. 陸生カタツムリの繁殖方法と技術は何ですか? 1. 環境が適切である。カタツムリを飼育する際は...
豚の鼻炎を効果的に予防・抑制する方法
導入豚鼻炎は、豚の上気道感染症を引き起こす病原体によって引き起こされる一般的な豚の病気です。鼻炎は豚...
天津にはオオゴイやニジマスを養殖している釣り公園はありますか?
釣りは毎年早春に始まります。飛行機工場の旧道の外環にある万楽漁村には清蓮漁村があるが、ルアーの穴への...
黒鯉を飼育する場合、ペレット飼料と押出飼料のどちらを与えた方が良いでしょうか?
1. 黒鯉を飼育する場合、粒状飼料と押出飼料のどちらを与えるのが良いですか?現在、ニシンの餌として...
双子豚の養殖 - 効率的な農業モデル
双子豚飼育の定義と利点双豚飼育とは、2匹の子豚を同時に産ませる飼育方法を指します。双子の豚を育てるこ...
子豚の離乳技術を習得し、健康に成長するための最善の方法を確保しましょう
導入離乳は子豚の繁殖過程において重要なステップです。正しい離乳時期と離乳方法は、子豚の成長、発育、健...
蚕はどこで捕れるのでしょうか?
分野。蚕は主に2つのカテゴリーに分けられます。1つは家蚕、つまり桑蚕です。主に桑の葉を食べます。もう...
1エーカーのミミズに投資するにはいくらかかりますか(1エーカーのミミズは1か月でどれくらいの利益を上げることができますか)
1. ミミズを1エーカーあたり飼育するにはどれくらいの費用がかかりますか? 1エーカーの土地の養殖...
放し飼い鶏の死亡原因と予防策の解明
放し飼いの鶏の死亡原因放し飼いの鶏が死ぬ理由はいろいろ考えられます。以下では、栄養、環境、感染症など...
新しい池に稚魚を入れるときに注意すべきことは何ですか?
1. 新しい池に稚魚を入れるときに注意すべきことは何ですか?新しい池に稚魚を放流する場合は、消毒、...