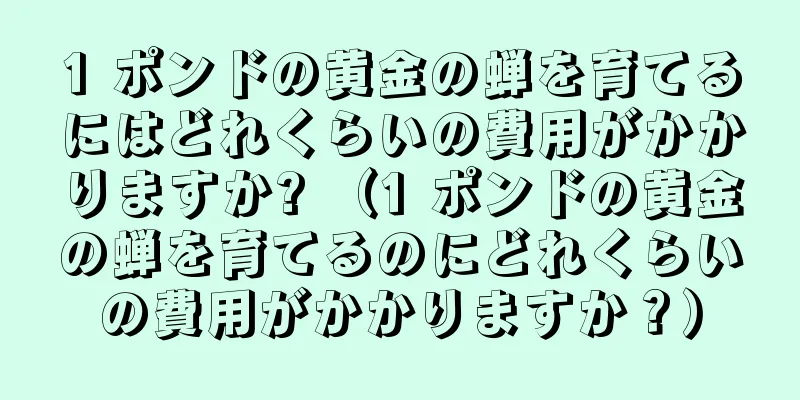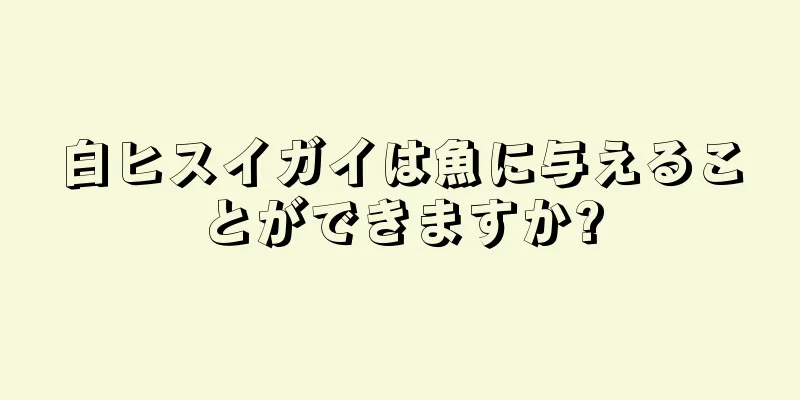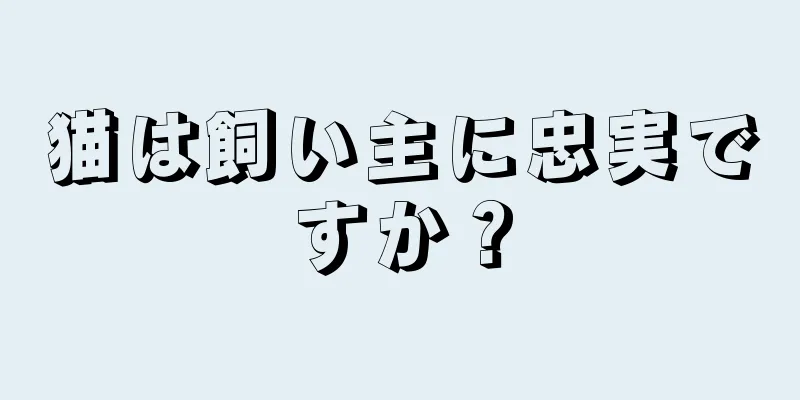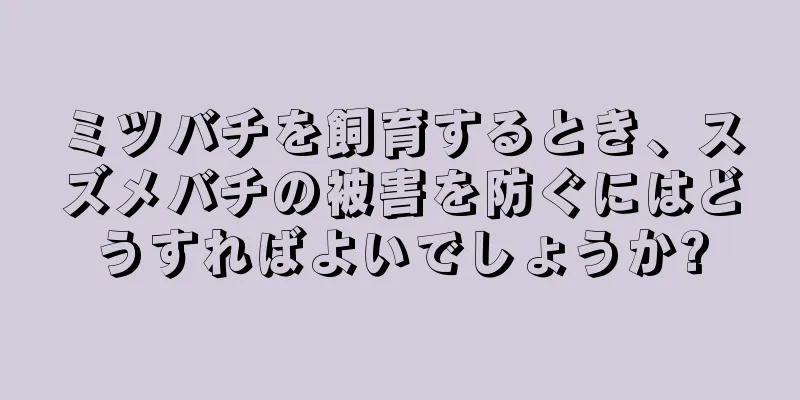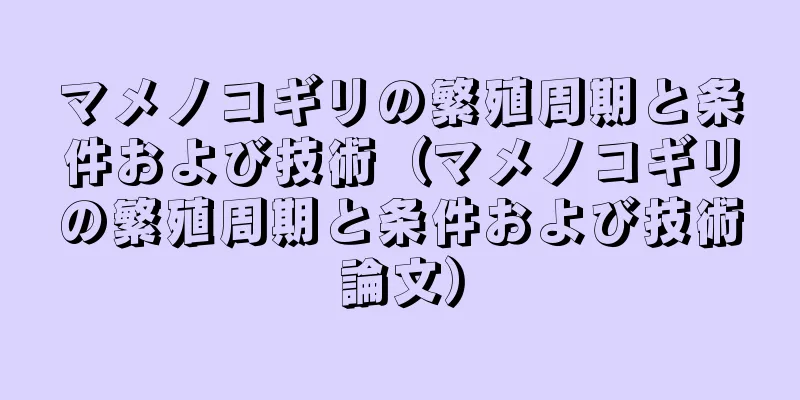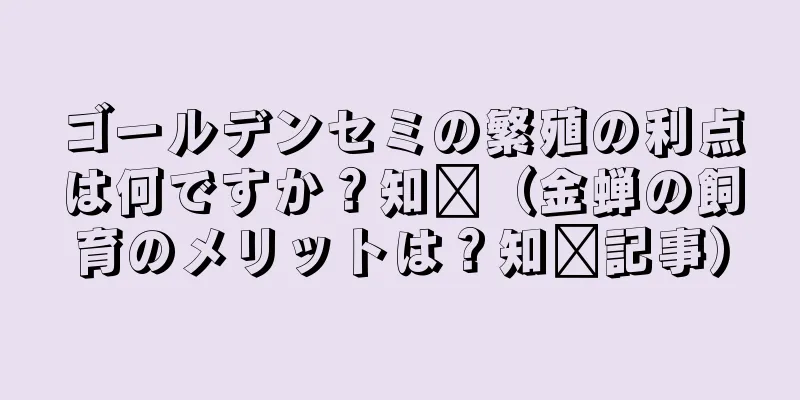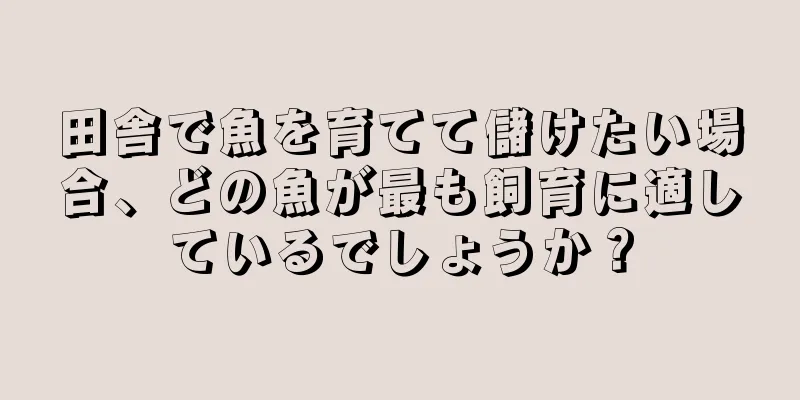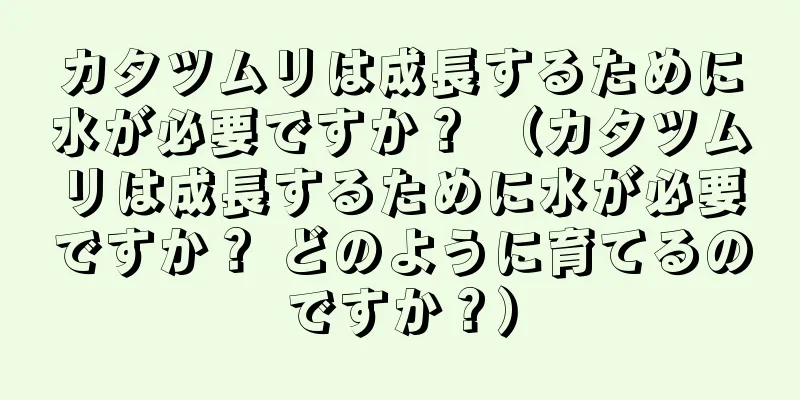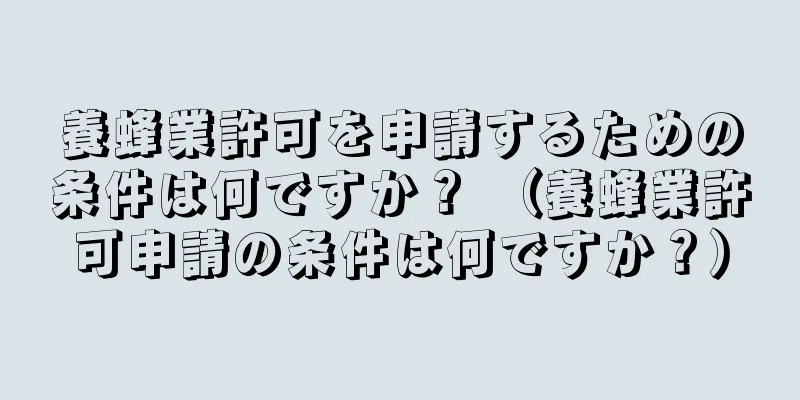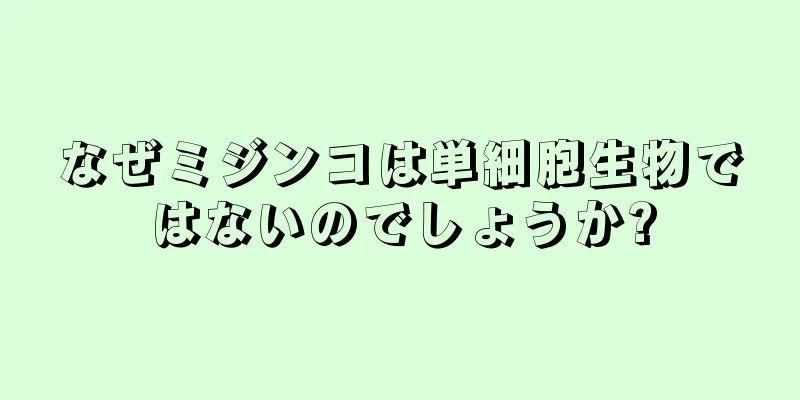エビの池の苔を防ぎ、除去するにはどうすればよいでしょうか?
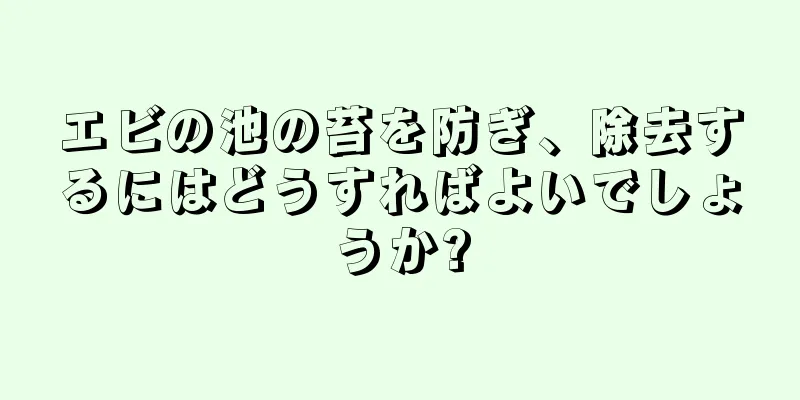
|
春になり水温が上がると、池の浅瀬に苔が生え始め、緑の糸状に成長して水面に浮かび、絡み合った糸の塊を形成します。エビの稚魚や稚エビは苔の中に泳ぎ込んで絡まって死んでしまうことがよくあります。エビ養殖池の苔を予防および除去するための主な方法は次のとおりです。 (1)池を徹底的に掃除した後は、苔の発生を防ぐためにすぐに水質に肥料を与える必要があります。水深は初期段階では50cm、後期段階では徐々に1.2mまで深め、透明度は30~35cmにします。苔が生えてきたら早めに対策を講じる必要があります。薬剤を使用して局所的に駆除することはできますが、手作業で除去すると、苔がさらに生える結果になることがよくあります。 (2)苔を殺すために硫酸銅または苔取り剤を使用する:一般的には、水1立方メートルあたり硫酸銅0.7グラムを使用します。使用後20時間経過したら適宜水を交換してください。苔取り剤を土に混ぜて乾かしながら撒くと、水をかけるよりも効果的です。枯れた苔を取り除いた後、発酵有機肥料を適時に施用します。一般的には 1 ムーあたり 100 ~ 150 kg の施用量です。その後、水質の変化に応じて適切な追肥を施し、水域の肥沃度を一定に保ち、苔の再出現を防ぎます。 (3)尿素は苔に対しても殺虫効果があります。苔に直接散布し、3~5日後に再度散布します。 (4)木灰を20~30kg/畝の割合で散布する。 (5)マツ葉スラリーの散布:水面1エーカーあたり新鮮なマツ葉10kgを水に浸して粉砕し、水を加えて25kgのスラリーを作り、1日1回池全体に散布する。 2~3日間手で慣らし続けます。 付録 付録1 無公害食用淡水エビ(NY 5158-2005) 1 適用範囲 この規格は、無公害淡水エビの要求事項、試験方法、検査規則、表示、包装、輸送および保管について規定する。 この規格は、Macrobrachium rosenbergii、Macrobrachium nipponensis、Penaeus vannammi および Procambarus clarkii の生きた生鮮品に適用されます。他の淡水エビもこの基準を参考にして実施することができます。 2 規範的参照 以下の文書の条項は、この規格で参照されることにより、この規格の条項となる。日付の付いた参照文書については、それ以降のすべての修正(正誤表を除く)または改訂は、この規格には適用されません。ただし、この標準に基づく契約の当事者は、これらの文書の最新バージョンを使用できるかどうかを調査することをお勧めします。日付の記載がない参照文書については、最新バージョンがこの規格に適用されます。 GB/T5009.11 食品中の総ヒ素及び無機ヒ素の測定 GB/T5009.12 食品中の鉛の測定 GB/T5009.15 食品中のカドミウムの測定 GB/T5009.17 食品中の総水銀及び無機水銀の測定 NY5051 無公害食品淡水養殖用水の品質 SC/T3015 水産物中のオキシテトラサイクリン、テトラサイクリン及びクロルテトラサイクリンの残留物の測定 SC/T3016-2004 水産物のサンプリング方法 3 要求事項 3.1 官能的要求事項 3.1.1 生きたエビ 生きたエビは、体の色と光沢が正常で、均整がとれており、形状が正常で、機敏で、病気にかかっていない。 3.1.2 新鮮なエビ 新鮮なエビは表1の要件を満たす必要があります。 表 1 感覚的要件 項目 要件 形態 エビの体は損傷がなく、結合膜が 1 か所以上破損していないこと。エビの体は明るい外観をしており、殻は光沢があります。エビの頭には黒い斑点や黒い円があってはなりません。匂い 匂いは普通で、特異な匂いはありません。筋肉組織は引き締まっていて弾力性があります。茹でテスト 茹でた後はエビ本来の旨味が残り、味は締まり弾力があります。注:形状、匂い、筋組織で品質を判断できない場合は、煮沸試験を実施します。 3.2 安全指標安全指標は表2の要件を満たす必要があります。 表2 安全指標 項目 指標 水銀(Hg)、mg/kg ≤0.5 ヒ素(As)、mg/kg ≤0.5 表 2 安全性指標 (続き) -1 項目 指標 鉛 (Pb で測定)、mg/kg ≤0.5 カドミウム (Cd で測定)、mg/kg ≤0.5 オキシテトラサイクリン、mg/kg ≤100 注: その他の農薬および動物用医薬品は、関連する国内規制に準拠する必要があります 4 試験方法 4.1 官能試験 4.1.1 明るく臭いのない環境で、サンプルを白いエナメルトレイまたはステンレススチールの作業台に置き、第 3.1 条の要件に従って各項目を検査します。 4.1.2 沸騰試験:臭いが出ない容器に飲料水500mLを加える。水が沸騰したら、サンプルを約100g取り、きれいな水で洗い、容器に入れて蓋をし、5分間煮沸し、蓋を開けて匂いを嗅いでから肉を味わいます。 4.2 総水銀の測定は、GB/T5009.17の規定に従って実施するものとする。 4.3 総ヒ素の測定は、GB/T5009.11の規定に従って実施するものとする。 4.4 鉛の測定はGB/T5009.12の規定に従って実施するものとする。 4.5 カドミウムの測定はGB/T5009.15の規定に従って実施するものとする。 4.6 オキシテトラサイクリンの測定は、SC/T3015の規定に従って実施されるものとする。 5 検査規則 5.1 バッチ規則とサンプリング方法 5.1.1 バッチ規則 同じエビ養殖池または養殖場で同じ条件で生産された生きたエビは、1 つの検査バッチとみなされます。同じ産地と大きさで生産された新鮮なエビは、1 つの検査バッチとみなされます。 5.1.2 サンプリング方法はSC/T3016の規定に従わなければならない。 5.1.3 サンプルの準備は、SC/T3016の付録Cの規定に従って行うものとする。 5.2 検査区分 製品は工場(現地)検査と型式検査に分けられます。 5.2.1 工場検査 製品の各バッチは工場(現場)検査の対象となる。工場(現地)老化検査は生産者自身が実施し、検査項目は官能検査とする。 5.2.2 型式検査 型式検査は、次のいずれかの状況が発生した場合に実施するものとし、検査項目は、この規格に規定する全項目とする。 a) 新しく建設された養殖場で養殖されたエビb) 農業条件が変化し、生産物の品質に影響を及ぼす可能性がある場合c) 関係行政部門が型式検査を要求する場合d) 最終検査と前回の型式検査との間に重大な相違がある場合e) 通常生産期間中は、少なくとも年に1回は定期検査を実施します。 5.3 判定規則 5.3.1 活エビ及び生鮮エビの官能検査項目は、すべて第3.1条の規定に適合しなければならない。結果はSC/T3016の表1の規定に従って決定されるものとする。 5.3.2 検査結果の安全指標の1つ以上が不合格の場合、その製品バッチは不合格と判断され、再検査は行われません。 6 表示、包装、輸送および保管 6.1 表示 製品には、その名称、原産地、製造者の名称および住所、製造日を記載する必要があります。 6.2 包装 6.2.1 包装材料 包装材料は、丈夫で、清潔で、無毒で、臭いがないものである必要があります。 6.2.2 包装要件 6.2.2.1 生きたエビは十分な酸素とともに包装する必要があり、水質は NY5051 の要件を満たす必要があります。 6.2.2.2 新鮮なエビは清潔な魚箱または孵卵器に入れて、エビの体温を0℃から4℃に保つ必要があります。エビの体への外部からの損傷を避けてください。 6.3 輸送 6.3.1 生きたエビを輸送する際は、十分な酸素を供給する必要があります。 6.3.2 新鮮なエビは、エビの体温を0℃から4℃に保ちながら、冷蔵または断熱された車両または船舶で輸送する必要があります。 6.3.3 輸送手段は清潔で無毒、無臭でなければならず、輸送による汚染は厳重に防止されなければならない。 6.4 保管 6.4.1 生きたエビを保管する場合は、十分な酸素を供給する必要があります。一時的な水の使用はNY5051の規定に従う必要があります。 6.4.2 新鮮なエビを保管する場合、エビの体の温度は0℃から4℃に保つ必要があります。 6.4.3 保管環境は清潔で、無毒、無臭、無公害であり、衛生要件を満たしている必要があります。 付録2 無公害淡水エビ養殖技術仕様(NY/T 5285-2004) 1 適用範囲 この規格は、淡水エビ(学名:Macrobrachium nipponensis)の無公害養殖における環境条件、種苗繁殖、種苗栽培、食用エビの飼育、エビの病気の予防および制御技術について規定する。 この基準は無公害のエビ養殖池に適用でき、水田農業の参考としても活用できます。 2 規範的参照 以下の文書の条項は、この規格で参照されることにより、この規格の条項となる。日付の記載された参照文書については、それ以降のすべての修正(正誤表を除く)または改訂は、この規格には適用されません。ただし、この標準に基づく契約の当事者は、これらの文書の最新バージョンを使用できるかどうかを調査することをお勧めします。日付の記載がない参照文書については、最新バージョンがこの規格に適用されます。 GB13078 飼料衛生基準 GB18407.4-2001 農産物の安全性と品質 無公害水産物の生産環境 NY5051 無公害食品淡水養殖水質 NY 5071 無公害食品漁業薬品使用ガイドライン NY5072 無公害食品漁業配合飼料安全限度 SC/T1008 稚魚と稚魚の従来の池養殖技術仕様「水産養殖品質と安全管理条例」中華人民共和国農業部令(2003)第[31]号 3 環境条件 3.1 場所の選択 水源が適切で、灌漑と排水が便利で、水の入口と出口が分離しており、農場の周囲 3km 以内に汚染源がないこと。 3.2 水源と水質 水質は淡水で、NY 5051 の要件に準拠し、溶存酸素レベルが 5 mg/L 以上、pH が 7.0~8.5 である必要があります。 3.3 エビ養殖池の状態 エビ養殖池は長方形で、東西方向に向いており、土壌はロームまたは粘土です。主な条件は表1に示すとおりです。完全かつ独立した給水・排水システムが備わっています。 表 1 エビ養殖池の状況 池の種類 面積 (m2) 水深 (m) 池堤内側勾配 水草植栽面積比率 (m2) 淡水エビ養殖池 1 000-3 000 約 1.5 1:3-4 1/5-1/3 種苗養殖池 1 000-3 000 1.0-1.5 食用エビ養殖池 2 000-6 700 約 1.5 1:3-4 1/5-1/3 3.4 エビ養殖池の底質 エビ養殖池の底は平坦で、シルトの厚さは 15 cm 以下である。底面の品質はGB 18407.4-2001の3.3の要件を満たしています。 4 苗の繁殖 4.1 親魚の供給源 親魚としては、川、湖、溝、その他の水質の良好な水域で捕獲された野生の淡水エビを選択する必要があります。病気がなく、健康で、体長が 4 cm 以上で、性的に成熟している必要があります。あるいは、繁殖期に卵を抱いた5cm以上の淡水エビを親エビとして直接購入することもできます。親魚は繁殖前に検疫する必要があります。 4.2 飼育密度:親魚1,000m2あたり45~60kg、雌雄比は3~4:1。 4.3 飼料と給餌 親魚飼料は主に配合飼料であり、給餌量は親魚の体重の2%~5%です。飼料の安全限度はNY5072の規定に準拠し、高品質の無毒、無害、無公害の新鮮な動物飼料を適切に添加し、給餌量は親魚の体重の5%から10%です。 4.4 親魚の産卵 水温が18℃を超えると、親魚は交尾をし、卵を産み始めます。卵を抱えたエビは地上のカゴで捕獲され、その後、種苗養殖池で育てられ、孵化されます。卵を抱えた野生のエビを購入し、種苗栽培池に移して育て、孵化させることもできます。 4.5 抱卵エビの孵化 抱卵エビの飼育密度は1000m2あたり12~15kgです。エビの卵の色に応じて、同様の胚発育段階にある抱卵エビを選択し、同じ池に入れて孵化させます。エビの孵化過程中は、水を新鮮に保つために毎日水を流してください。通常、エビの卵が孵化するまでには20日から25日かかります。エビの卵が透明になり、胚に目玉模様が現れたら、分解した無公害有機肥料を1,000m2あたり150~450kg施用します。産卵エビの 80% 以上が孵化して幼生になったら、地上トラップを使用して親エビを捕獲します。 5. 苗の栽培 5.1 幼虫密度 池の幼虫の飼育密度は 2,000 匹/m2 以下に管理する必要があります。 5.2 給餌 5.2.1 第一段階では、孵化池で幼虫が見つかったら、すぐに豆乳を与える必要があります。給餌量は1,000m2あたり1日2.5kgの豆乳で、その後徐々に1日6.0kgまで増やしていきます。給餌方法:毎日8:00~9:00と16:00~17:00に1回給餌してください。 5.2.2 第2期幼生が孵化してから3週間後、徐々に豆乳の給餌量を減らし、淡水エビの種苗用配合飼料の量を増やします。配合飼料の安全限度はNY5072の規定に準拠する必要があります。配合飼料を1週間与えた後、1日の給餌量は30kg/hm2~45kg/hm2で、給餌時間は毎日17:00~18:00です。 5.3 施肥 幼生が孵化した後、水中のプランクトン量と幼生の摂食状況に応じて、約 15 日以内に分解された有機肥料を施用する必要があります。 1回あたりの施肥量は1,000m2あたり75kg~150kgです。 5.4 間引き 稚エビが 0.8cm~1.0cm に成長したら、飼育池の密度に応じて適時に間引きを行う必要があります。稚エビの飼育密度は1,000匹/m2以下に管理する必要があります。 5.5 養殖池の水質要件:透明度約30cm、pH7.5~8.5、溶存酸素≥5mg/L。 5.6 エビの稚魚の収穫 養殖開始から20~30日後、稚エビが1.0cm以上に成長すると、エビの稚魚を収穫し、食用エビの養殖段階に入ります。エビの稚魚は、密網や引き網を使用したり、放水して集めたりすることで捕獲できます。 6. 食用エビの養殖 6.1.池の状態 6.1.1.給水口の要件 給水口は、メッシュ サイズが 0.177 mm ~ 0.250 mm の篩シルク製フィルター バッグを使用してろ過する必要があります。 6.1.2 サポート施設 淡水エビの飼育に主に使用される池には、水ポンプやエアレーション装置などの機械設備を備える必要があります。水面1ヘクタールあたり4.5kW以上の出力を持つ曝気装置を設置する必要があります。 6.2 放流前の準備 6.2.1 池の清掃および消毒は、SC/T 1008 の規定に従って実施しなければならない。 6.2.2 水生植物の植栽 水生植物の植栽エリアは、この規格の4.2に準拠する必要があります。植えられる水生植物の種類には、Vallisneria、Hydrilla verticillata、Potamogeton oleifera、Elodea などの沈水植物や、ウォーターピーナッツやウォータースピナッチ(ウォータースピナッチ)などの水生植物が含まれます。 6.2.3 稚エビを放流する5~7日前に、池に50~60cmの深さまで水を注ぎ、施肥します。同時に、プランクトンを養殖するために、分解された有機肥料を2,250〜4,500 kg/hm2施用します。 6.3 エビの稚魚の放流 6.3.1 放流方法 放流には晴天の日を選んでください。放流する前に、池の水を取ってエビの稚魚をテスト養殖します。池の水が稚エビに悪影響を与えないことが確認されたら、稚エビの正式な放流を開始できます。稚エビを飼育する際の温度差は±2℃以内に抑えてください。エビの稚魚の捕獲、輸送、および放流は水中で行わなければなりません。 6.3.2 養殖モデルと飼育密度 6.3.2.1 1 シーズンのエビの稚魚養殖の場合、養殖モデルは、一度に十分な数のエビの稚魚を放流し、大きいものを捕獲し、小さいものを年間を通して飼育することです。放流密度:1月から3月にかけて、1平方メートルあたり60万~75万匹(1kgあたり約2,000匹)の稚エビを放流します。あるいは、7月から8月にかけて全長1.5cmから2cmの稚エビ90万~120万匹/m2が放流される。エビの稚魚を放流してから15日後、池の混合養殖仕様は、体長15cmのハクレンとコイが1,500〜3,000匹/hm2、または夏コイとコイが22,500匹/hm2でした。食用エビを捕獲するための主な手段は、落とし穴漁業です。 6.3.2.2 多シーズン養殖 揚子江流域では二シーズン養殖が行われていますが、珠江流域では三シーズン養殖が可能です。 放流密度:越冬稚エビの大きさは2,000匹/kg、放流量は450,000匹/hm2~600,000匹/hm2。稚エビの大きさは1.5cm~2cm、放流量は60万尾/m2~80万尾/m2です。放流時期:一般的には7月から8月、12月から翌年3月まで。エビの稚魚を放流してから 15 日後に、池には 1,500 ~ 3,000 匹の 15 cm サイズのギンコイとコイが /hm2 あたり、または 22,500 匹のギンコイとコイが /hm2 あたり混泳されます。 6.3.2.3 魚類とエビ類の複合養殖 単位生産量 7,500 kg/hm2 の食用魚養殖池または非肉食魚類の稚魚養殖池では、新鮮なエビを一緒に養殖し、エビの稚魚の放流密度は一般に 150,000 匹から 300,000 匹/hm2 の範囲とします。養殖池における新鮮な稚エビの放流量は適宜増やすことが可能であり、放流時期は一般的に冬と春に行われる。 6.3.2.4 エビ、魚、カニの混合養殖放流パターンと放流量を表2に示す。 表 2 エビ・魚・カニ混合養殖の放流表 品種 規格 放流量 放流時期 生エビ 全長 2cm~3cm 450,000 匹/hm2 1 月~3 月 カワガニ 100 匹/kg~200 匹/kg 4 500 匹/hm2 1 月~3 月 ニシキヘビ 体長 5cm~10cm 225 匹/hm2~300 匹/hm2 7 月 コイ 0.5kg/尾~0.75kg/尾 150 匹/hm2~225 匹/hm2 1 月~3 月 6.4 給餌管理 6.4.1 飼料給餌 飼料給餌は「四定」の給餌原則に従い、定質、定量、定位置、定時を実現する。 6.4.1.1 飼料要件 エビ用配合飼料の使用が推奨されます。配合飼料はカビや劣化がなく、汚染されていないものでなければなりません。安全限度要件は、NY 5072 の規定に準拠する必要があります。単一飼料は、口当たりがよく、カビや劣化がなく、汚染されていないものでなければなりません。その衛生指標は GB 13078 の規定に準拠する必要があります。新鮮な飼料は新鮮で、口当たりがよく、腐敗や劣化がなく、無毒で汚染のないものでなければなりません。 6.4.1.2 給餌方法:1日2回、8:00~9:00と18:00~19:00に1回ずつ給餌します。朝に与える量は1日の総給餌量の1/3で、残りの2/3は夕方に与えます。餌は池の端から1.5m離れた水中に、複数の点または線状に与えます。 6.4.1.3 給餌量 エビの飼育期間中の各月の配合飼料の1日あたりの給餌量は表3の通りです。実際の給餌量は天候、水質、水温、摂餌および脱皮条件などに応じて柔軟に管理し、給餌量を適切に増減する必要があります。 表 3 淡水エビ飼育における各月の配合飼料の 1 日給餌量 月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 日給餌量 (%) 1.5~2 2~3 3~4 4~5 5 5 5 5~4 4~3 26.4.2 水質管理 6.4.2.1 飼育初期 (3 月~5 月) は池水の透明度を 25cm~30cm に、中期 (6 月~7 月) は透明度を 30cm に、後期 (8 月~10 月) は透明度を 30cm~35cm に管理する。溶存酸素は4 mg/L以上に維持されました。 pH7.0~8.5。 6.4.2.2 施肥と水量調整 養殖水質の透明度の変化に応じて、適時に肥料を与える必要があります。一般的に、分解有機肥料は養殖初期には10~15日に1回、中期・後期には15~20日に1回施用します。 1回あたりの施肥量は750kg/hm2~1500kg/hm2です。 6.4.2.3 新しい水への交換 養殖の初期段階では、水は交換せず、7〜10日に1回、10cm〜20cmの新しい水を追加します。中期には15~20日に1回水を交換します。後期段階では、水は週に1回、1回につき15cm~20cmの水で交換されます。 6.4.2.4 生石灰の使用 エビ養殖期間中、生石灰は15日から20日に1回使用し、1回の使用量は150kg/hm2です。スラリー状にした後、池全体に均等に散布します。 6.4.3 日常管理 6.4.3.1 毎日午前と夕方に1回ずつ池を巡回し、水の色の変化、エビの活動、摂食状況を観察します。池の基礎部分に漏れがないか、また逃亡防止設備が損傷していないかを確認します。 6.4.3.2 エアレーション成長期間中、エアレーション装置は通常、毎日早朝と正午に1回ずつ、それぞれ1.0時間から2.0時間作動します。雨の日や気圧が低い場合はスタート時間が延長されます。 6.4.3.3 生育と病気の検査 7~10日に1回、50匹以上のエビをサンプリングし、エビの生育と給餌状況を確認し、病気の有無を確認します。これは、給餌量と薬剤の使用を調整するための基礎として使用されます。 6.4.3.4 記録養殖生産記録は、中華人民共和国農業部令(2003)第[31]号「養殖業の品質と安全の管理に関する規則」に定められた様式に従って保管しなければならない。 7 病気対策 7.1 エビの病気対策の原則 無公害エビ養殖の過程における病気の予防と対策では、予防第一、総合的な対策の原則を堅持する必要があります。予防・治療薬の使用はNY 5071の要件に準拠し、動物用医薬品登録証明書、製造承認証明書、実施承認番号を取得する必要があります。また、中華人民共和国農業部水産養殖業品質安全管理条例(2003年)第31号に規定される形式で薬物使用の記録を保管する。 7.2 一般的なエビの病気の予防と管理 淡水エビ養殖でよく見られる病気には、赤体病、黒鰓病、黒点病、寄生性原虫病などがあります。具体的な予防と管理方法は表4に示されています。 表4 一般的なエビの病気の治療法 エビの病気名 症状 治療法 休薬期間 注意事項 赤体病 病気の初期段階では、エビの尾が赤くなり、次に遊泳脚と腹部全体に広がり、最終的に頭部、胸部、歩脚がすべて赤くなります。病気のエビは動きが鈍くなり、食欲が減退したり、食べなくなったりし、ひどい場合には大量死を引き起こすこともあります。 1. 池全体に二酸化塩素を散布します。用量:0.1mg/L~0.2mg/L、ひどい場合は0.3mg/L~0.6mg/L。 2. 餌にスルファメトキサゾール100mg/kg体重またはフロルフェニコール10mg/kg体重を混ぜ、5~7日間連続で与え、初日は投与量を2倍にします。予防には、投与量を半分に減らし、3日から5日間継続して使用してください。 3. ポビドンヨードを池全体に散布します(幼エビ:0.2mg/L〜0.5mg/L、成エビ:1mg/L〜2mg/L) 二酸化塩素≥10日、スルファメトキサゾール≥30日、フロルフェニコール≥7日 1. 二酸化塩素には金属製の容器を使用しないでください。他の消毒剤と混ぜないでください。2. スルファメトキサゾールは酸性の薬剤と一緒に使用できません。3. ポビドンヨードは金属物と接触させないでください。第四級アンモニウム消毒剤と直接混ぜないでください 表4 一般的なエビの病気の治療法(続き)-1 エビの病気名 症状 治療法 休薬期間 備考 黒鰓病 罹患したエビの鰓糸は黒くなり、部分的にカビが生えている。病気のエビの中には、頭胸部と腹甲の側面に黒い斑点が現れるものもあります。病気にかかった若いエビは、活力が低下し、底をゆっくりと泳ぎ、走光性が弱まり、変態期間が長引くか変態に失敗し、腹部が丸まり、青白くなり、餌を食べなくなります。成体のエビが病気になると、水面に浮かんで動きが遅くなることがよくあります。 1. 細菌による黒鰓病:餌にオキシテトラサイクリン 80 mg/kg 体重またはフロルフェニコール 10 mg/kg 体重を混ぜ、5~7 日間連続で与え、初日は投与量を 2 倍にします。予防には、用量を半分にして3日から5日間継続して使用してください。 2. 水中の浮遊有機物が多すぎることによる黒鰓病:定期的に池全体に15mg/L~20mg/Lの生石灰を散布します。漂白剤 ≥5d、オキシテトラサイクリン ≥21d、フロルフェニコール ≥7d。 1. オキシテトラサイクリンをアルミニウム、マグネシウムイオン、ハロゲン、重炭酸ナトリウム、ジェルと一緒に使用しないでください。 2. 生石灰を漂白剤、有機塩素化合物、重金属塩、有機錯体と混ぜないでください。黒点病はエビの甲羅に黒い潰瘍の斑点を引き起こします。ひどい場合には、エビの活力は著しく低下し、池の端で瀕死の状態になります。親エビの殻の損傷を防ぐために、水を清潔に保ち、釣り、輸送、放流の際には水を携行してください。発症後はポビドンヨード(幼エビ:0.2mg/L~0.5mg/L、成エビ:1mg/L~2mg/L)を池全体に散布してください。ポビドンヨードは金属物と接触しないようにしてください。第四級アンモニウム消毒剤と直接混ぜないでください。寄生性原生動物を顕微鏡で調べたところ、線虫、凝集虫、釣鐘虫、吸殻虫がエビの体と鰓に寄生していることがわかりました。ひどい場合には、綿毛の層が肉眼で見えることもあります。 1. 池全体に1mg/L~3mg/Lの硫酸亜鉛を散布します。 2. 池全体に硫酸亜鉛とともに1mg/Lの過マンガン酸カリウムを7日間以上散布します。 1. 硫酸亜鉛を保管する際には金属製の容器を使用しないでください。使用後は池の酸素化に注意してください。過マンガン酸カリウムは強い日光の下では使用しないでください。 |
推薦する
1 トンの牛糞から何立方メートルのバイオガスを生産できますか? (牛糞1トンから何立方メートルのバイオガスが生産できるかを示すビデオ)
1. 100 トンの牛糞からどれくらいのバイオガス残渣と液体バイオガスを生産できますか? 100 ...
理想的な鶏小屋の作り方
導入養鶏農家にとって、良い鶏舎を建てることは、鶏の健康と生産力を確保するための鍵となります。大規模農...
カタツムリ飼育の害(カタツムリ飼育は人体に有害か)
1. カタツムリを飼育することのメリットとデメリットは何ですか?利点: カタツムリの養殖は収益性が...
黄色い魚の名前は何ですか?
黄色い魚の名前は何ですか?この黄色い魚はPelteobagrus fulvidracoと呼ばれていま...
ミミズを太く大きく育てて、飼いやすくする方法 (ミミズを太く大きく育てて、飼いやすくする方法)
1. ミミズを太く強く育てるにはどうすればいいですか?ミミズは発酵した牛糞を餌として与えられます。...
田舎の土壁には、たくさんのミツバチが巣を作ったり、穴を掘ったりしています。これらは何の蜂ですか?
1. 田舎の土壁には、たくさんのミツバチが巣を作ったり穴を掘ったりしています。これらは何の蜂ですか...
レッドローズスパイダーの繁殖用土壌の価格はいくらですか?
レッドローズスパイダーの繁殖用土壌の価格はいくらですか?通常は花鳥市場で売られています。ネットで1個...
タラとハドックの違いは何ですか?
ギンダラは深海魚、海水魚であり、栄養が豊富です。いわゆる「タラ」との違いは何でしょうか?実はこれはタ...
ミミズは今貴重なのでしょうか?餌の与え方
1. 地元は今価値があるのか?餌の与え方ミミズは常に貴重な存在でした。うまく育てられるかどうかに...
ミツバチは花粉を集めるためにどの器官を頼りにしているのでしょうか?
1. ミツバチは花粉を集めるためにどの器官を頼りにしていますか?ミツバチは花の蜜だけでなく花粉も集...
チンチラ猫のグルーミング
チンチラ猫チンチラ猫はとても人懐っこくて愛らしいですが、とても清潔好きで、世話が少し面倒なこともあり...
ブダイの生活習慣と餌のガイドライン。
ブダイの生活習慣と餌のガイドライン。ブダイの寿命は4〜5年に達します。生物学的特徴:台湾原産で、レッ...
なぜ多くのフォーラムが閉鎖されているのでしょうか?
1. 現在、多くのフォーラムにアクセスできないのはなぜですか?今はカニの季節です~~~ほとんどのフ...
ハエを食べるのは栄養があるのでしょうか?
1. 人間がハエを食べるのは栄養になるのでしょうか?生物の基本単位はタンパク質と核酸であり、その中...
ジンチャンには専門の購買メーカーはいますか?
1. Jinchanには専門の購買メーカーがありますか?回答:Jinchanには専門の購買メーカー...